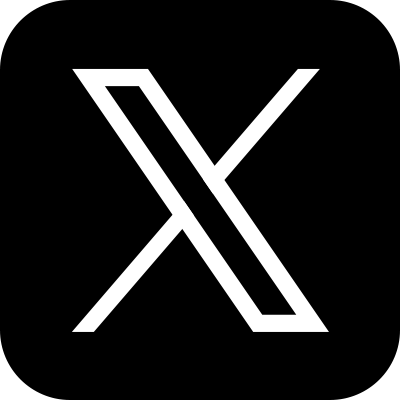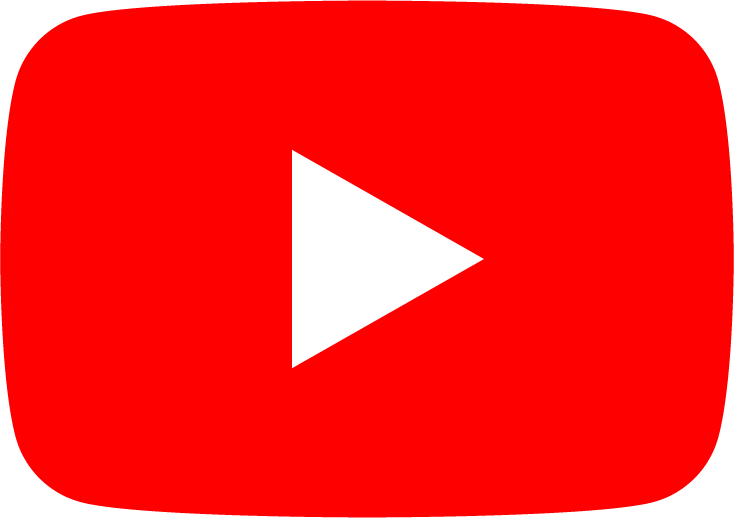- TOP
- 特集
- スーパー耐久(S耐)特集
- スーパー耐久ルール解説
- スーパー耐久ルール解説Vol.4 公式予選のスケジュール、グループ分けや順位決定の方法を解説
スーパー耐久ルール解説Vol.4 公式予選のスケジュール、グループ分けや順位決定の方法を解説
-

予選が始まる直前、一斉に動き出すマシン (c)スーパー耐久機構
決勝レースのスターティンググリッドを決めるために、公式予選が実施される。その予選にも手順があり基準タイムというものが設定されている。
耐久レースのため、予選結果がレースリザルトに与える影響は他のレースに比べると低いかもしれない。それでもライバルに負けじと挑むチームや、決勝レースを見越したセッティングを進めるチームなど、予選でもさまざまなドラマが展開される
目次
グループ分け
公式予選の順位決定方法
公式予選のスケジュール
基準タイム
ポールポジションのスタート位置
参加台数の上限を超えた場合
公式予選が行われなかった場合
予選中の赤旗
各サーキットの公式予選正式結果表
グループ分け
スーパー耐久シリーズには9つのクラスがあるので、同時に50台近い車両が一気にタイムアタックを行うと危険ということもあり、2グループ、3つの枠に区分して行われることが多い。
【主なグループの分け方】
第1グループ
- ST-Xのみ
- ST-Z、ST-TCR、ST-1、ST-2、ST-Qクラスの一部
第2グループ
- ST-3、ST-4、ST-5、ST-Qクラスの一部
※グループの分け方は、そのレースでのエントリー状況で変化する
※第1グループの中でも最も速いST-Xクラスは単独での予選となることが多い
※ST-QクラスはST-Zクラス相当~ST-5クラス相当まで混在するため、速さによってグループが分かれる
グループやドライバーごとに分かれて予選が行われるため、時間も長く、同じ車両が複数回走行するので、いろいろな場所でアタックを見ることも可能だ。
グリッド順を決める予選タイムを争うのはA、Bドライバーのみ
公式予選はA、Bドライバーのベストタイムの合算で順位が決まる
もし2台以上の車両が同タイムをマークした場合は、A、Bドライバーのセカンドベストタイムの合算により速い順とする。
またスターティンググリッド選抜の優先順位も決められている。
(1)A、Bドライバー共に予選通過基準ラップタイムをクリアできたチーム
(2)A、Bドライバーのどちらかのみ予選通過基準ラップタイムをクリアできたチーム
(3)A、Bドライバー共に予選通過基準ラップタイムをクリアできなかったチーム
C、Dドライバーはその予選における基準タイムをクリアすれば良い。
また富士24時間など長いレースではE、Fドライバーを起用するチームもあるが、その場合は予選としてではなくフリー走行として行われる。
公式予選のスケジュール
公式予選が続けて行われる場合は、Aドライバー用の公式予選50分間と、Bドライバー用の公式予選45分間が、10~15分間のインターバルを挟んで連続的に行われる。
(例)連続して行われる公式予選のスケジュール
| Aドライバー(50分間) | インターバル | Bドライバー(45分間) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2グループ | 第1グループ | 第2グループ | 第1グループ | |||
| ST-X以外 | ST-Xのみ | ST-X以外 | ST-Xのみ | |||
| 20分間 | 15分間 | 15分間 | 10~15分間 | 20分間 | 15分間 | 10分間 |
これが終了するとインターバルを挟みCドライバー予選、さらにインターバルを挟みDドライバー予選を行う。
ただしそのレースごとに時間やグループ分けなどはさまざまだ。
【2022年の例】
第1戦鈴鹿 C、Dドライバーとも、全クラス一緒で20分ずつ
第2戦富士 C、Dドライバーとも2グループに分かれ、それぞれ15分ずつ
第3戦SUGO Cドライバーは2グループに分かれ15分ずつ、Dドライバーは全クラス一緒で20分
基準タイム
A、B、C、Dドライバーは、基準タイムをクリアしなければ予選通過とはならない
それぞれの予選時間で達成された当該クラスの上位3位のタイムを平均し、その110%を基準タイムとする
つまりクラス上位3台の平均タイムが2分0秒0だとすれば、2分12秒0までのタイムを計測しておかなければならないということだ。
もしもマシントラブルやアタック中にセッションが中断したりするなどして、基準タイムをクリアできなかった場合には、公式予選不通過となり、決勝レースのスターティンググリッドは保留になる。
最終的なスターティンググリッドは大会審査委員会が決定する。
ポールポジションのスタート位置
決勝レーススタート前にコース上にマシンが並ぶスターティンググリッドは、左右2列に設置されている。予選の順位どおりに左右交互に車両が並べられるが、ポールポジションのグリッド位置は、すべてのサーキットにおいて1コーナーに向かってイン側とする。
- 決勝レースが1レースで行われる場合は、2グループに別れてのスターティンググリッドとなる。
(※フォーメーションラップは同時にスタートするが、ローリングスタートによる決勝スタート時には、グループごとに少し間隔を空けてスタートする。) - 決勝レースが2レースで行われる場合は、各々のレースとしてスターティンググリッドが配置される。
参加台数が決勝出走数を上回った場合
参加型のスーパー耐久シリーズは人気が高く、公式車検合格台数が決勝スターティンググリッド台数を超えることがある。
その際は、前年の各クラスチャンピオンチーム、そして主催者・STOが指定するチームを、大会の最大グリッド台数から差し引き、残った数に対し各クラスの出走可能台数を算出する。
クラスごとのグリッド台数は主催者が決めた按分比率により決定となる。
ただ、参加台数の多かった2014年の鈴鹿ラウンドでは、50台を2グループに分けて決勝レースを行いこの問題をクリア。2016年以降は、主に岡山国際サーキットとスポーツランドSUGOのレースで2グループに分けて決勝レースを行っている。
公式予選が行われなかった場合
公式予選が行われない大会においては、その決勝スターティンググリッドの決定は大会特別規則書にて明記される。
なお、2021年第3戦富士24時間では、荒天のために公式予選が行われず、そのレース前の時点のランキングと前日に行われた専有走行のタイムを参考にグリッドが決められた。
予選中の赤旗
予選中に中断の合図「赤旗」が出されたら、追い越しは禁止され、全車直ちにピットに戻りエンジンを停止する。ピットでは給油作業を含めすべての作業が認められる。
赤旗解除後の予選の再開、終了については、その時の状況をレースオフィシャルが判断し指示をすることとなる。
参考 各サーキットの公式予選正式結果表
2021第1戦 モビリティリゾートもてぎ(5時間/1レース)
2021第2戦 スポーツランドSUGO(3時間/2レース)
2021第4戦 オートポリス(5時間/1レース)
2021第5戦 鈴鹿サーキット(5時間/1レース)
2021第6戦 岡山国際サーキット(3時間/2レース)
グループ1 グループ2
2022第2戦 富士スピードウェイ(24時間/1レース)
(文:皆越和也 編集:GAZOO編集部 写真:スーパー耐久機構)
S耐規則書記事
-

-
スーパー耐久ルール解説Vol.7 シリーズポイント、出場奨励金、ペナルティポイントなどを解説
2022.09.07 特集
-

-
スーパー耐久ルール解説Vol.6 フルコースイエロー(FCY)、セーフティカー(SC)やレースの中断、再開、終了について解説
2022.08.01 特集
-

-
スーパー耐久ルール解説Vol.5 決勝レースのスタートからピット作業、チェッカーまでを解説
2022.07.08 特集
-

-
スーパー耐久ルール解説Vol.4 公式予選のスケジュール、グループ分けや順位決定の方法を解説
2022.07.04 特集
-

-
スーパー耐久ルール解説Vol.3 レース車両のパーツや車体の規定、タイヤ、燃料、車検などを解説
2022.07.02 特集
-

-
スーパー耐久ルール解説Vol.2 参加ドライバーの条件やプラチナ、ジェントルマン、エキスパートという種別を解説
2022.06.25 特集
-

-
スーパー耐久解説Vol.1 どんな車両が参加できるの? 成り立ちから、参加できる車両、クラス分け、性能調整を解説
2022.06.18 特集
こちらもおすすめ!S耐記事新着
-

-
「クルマ好きを笑顔に」。スーパー耐久で自動車メーカーがタッグを組む『共挑』の価値と可能性
2024.06.05 モータースポーツ
-

-
青山学院大学の自動車部が、スーパー耐久参戦を目指す活動とマシンを発表!
2024.05.31 モータースポーツ
-

-
楽しく学んで美味しく味わう。S耐富士24時間で水素やカーボンニュートラルがより身近に
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間 液体水素GRカローラは新たな課題を発見、総合優勝は連覇の1号車 ROOKIE AMG GT3
2024.05.26 モータースポーツ
-
-
富士24時間を夜も楽しむ キャンプだけでない
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
マツダがS耐で展開するステップアッププログラムがすごい! ロードスター・パーティレースのチャンピオンが集結
2024.05.26 モータースポーツ
-

-
「楽しくてしょうがない!」。近藤真彦“選手”が水素エンジンのGRカローラで16年振りにスーパー耐久に参戦!
2024.05.25 モータースポーツ
-
-
富士24時間 GRカローラの水素エンジンは更に深化
2024.05.25 モータースポーツ
-

-
立川祐路選手も参戦!タイのクルマ好きとコラボした日本の名門チームがスーパー耐久富士24時間でデビュー
2024.05.25 モータースポーツ
連載コラム
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08
-

-
HKSとスタディがコラボ、BMW向けアフターパーツブランド「HKSTUDIE」立ち上げ
2024.06.08
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08