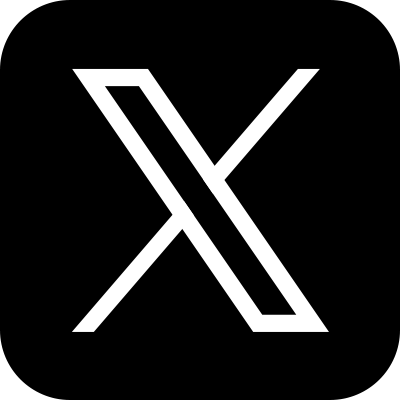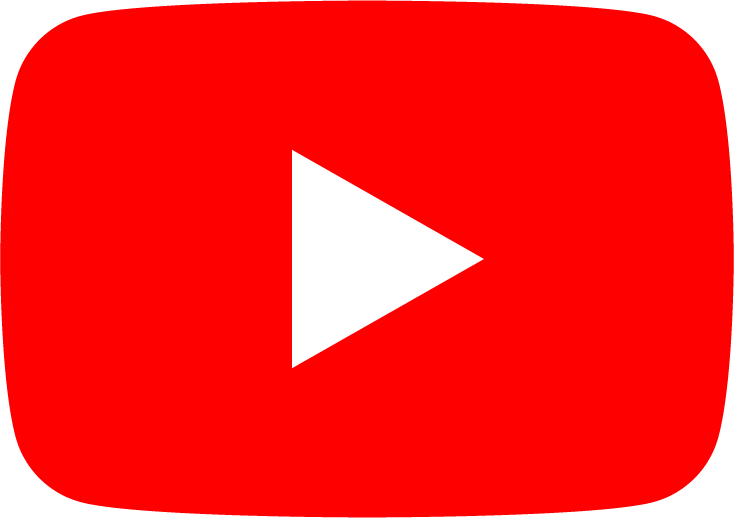北海道の人口5千人の町がFCEV車を導入。驚きの水素の原料とは?!
北海道十勝管内鹿追町は大雪山国立公園の山麓にある農業を基幹産業とする町です。
鹿追町では、2022年度から水素を燃料として走る燃料電池自動車(FCEV車)を公用車として10台導入しました。
なぜ鹿追町でFCEV車を多数導入するに至ったのか、燃料となる水素はどう供給しているのかなどを、北海道鹿追町農業振興課環境保全センター 課長の城石賢一さんに伺いました。
燃料電池自動車を公用車に10台、町内の事業者でも9台導入
――2022年度に燃料電池自動車(FCEV車)を公用車として導入されたそうですね。
トヨタ自動車「MIRAI(ミライ)」を町の公用車として10台、そして、町内のJAや金融機関、土木建設会社などの事業者さんでも合わせて9台、合計で19台を導入することになりました。
-

ミライの燃料電池システム
――クルマとしてもかなり高価なものと聞いていますが
やはり新車となるとなかなか手が出しにくいところですが、東京オリンピック・パラリンピックで使用されたFCEV車を譲り受けることができるとのことで、その車両を導入することができました。
家畜のふん尿をバイオガス化。そして水素に
――FCEV車を使用したくても、肝心の水素がなければ導入できませんよね?
鹿追町では家畜のふん尿をいかして水素をつくり、供給しています。
――家畜のふん尿ですか?!
はい。家畜のふん尿をバイオガス化しメタンガスを抽出、そこから水蒸気改質と呼ばれる方法で水と反応させて水素を製造し、利用しています。
農業、酪農が基幹産業である鹿追町では家畜のふん尿が大量に発生します。鹿追町環境保全センターにて、家畜のふん尿を適正処理し、そこから得られるエネルギーを最大限活用する事業を2007年より始めました。
ふん尿をメタン発酵させてメタンガスを主成分とするバイオガスを作り出し、発電機の燃料として利用するというものです。
そして、このような再生可能エネルギーは、固定価格買取制度(FIT)により20年間はそれなりの価格で買い取りしてもらえることになっています。
-

鹿追町環境保全センター全景
しかし、20年間を過ぎてしまうと、買取価格はかなり落ちてしまいます。バイオプラントを維持・運営させるためには、一定の収益が必要ですが、買取価格が落ちるとその分の費用が見込めません。
そこで、新たなエネルギーの形でバイオガスを活用できないかと模索し、環境省の委託を受け、家畜ふん尿由来の水素の製造から供給まで、一貫したサプライチェーンの構築をするという実証事業に取り組むことになったのです。
この実証事業は民間企業さんを中心に2015年度から2021年度まで行いました。
「しかおい水素ファーム®」を新たに整備して水素をつくり、水素ステーションを通じてFCEV車や燃料電池フォークリフトにも使用しました。
他にも、純水素型燃料電池の燃料として輸送し、町内のチョウザメ飼育施設や帯広市のばんえい競馬場、帯広動物園といった遠くでも利用するなど7年間にわたり実験をしてきました。
-

町内のチョウザメ飼育施設でも水素を利用
2021年度いっぱいでこの実証事業が終了したところで、培ったノウハウを今度は社会実装しようと、引き続き民間企業さんが中心となって新たな水素事業会社を設立、2022年4月1日から正式に稼働を始めました。
これからは、低炭素・脱炭素の社会を構築するべく、鹿追町内でも最大限活用していこうと、一番取り組みやすいクルマへの利用を始めました。
水素を活用した環境にやさしいまちづくりを
――水素は年間どのくらい生産できるのですか?
鹿追町の施設では年間60万Nm3(ノルマルリューベ)です。
ちなみにミライを満充電させるには、55 Nm3必要ですので、公用車10台を全部充電させても550 Nm3。満充電でおよそ500㎞走りますので、普通のガソリン車と同じくらいの燃費になるかと思います。
――ということは、かなりの量の水素が利用できるということですね。
そうですね。まだまだたくさんのクルマを走らせることができますし、燃料電池も増やすことができます。
ただ、北海道内の水素ステーションは本町と札幌市、室蘭市の3ヵ所しかありません。旭川市や帯広市など道内の拠点となる街に整備されていかないと、FCEV車の普及にはまだ難しい状況です。
水素のエネルギーとしての普及のためにも、本町にて「つくって貯蔵をし、運んで、利用する」という地産地消型のモデルケースとしての実証事業が行われたというところもあります。
――北海道のような寒冷地で水素を利用することの障害や危険性はないのでしょうか。
クルマに関しては、実証事業の間に5年間ほど使用していますが、寒冷地でもまったく問題はありませんでした。厳寒期に1週間くらいクルマを動かしていなくても、問題なく動きました。
ガソリンなどどんな燃料でも取り扱いを間違うと危険なことになりますよね。水素も同様で正しく取り扱えば危険はありません。
――今後はどのように水素の利用を展開していく予定ですか?
今回、公用車や町内事業者さんにある程度FCEV車を利用いただくことになりましたが、今後は、もっと町民の皆さんにも広く利用いただけるよう導入推進を図っていきたいです。合わせて、スクールバスや公共交通のバスなどにも活用していけたらと考えています。
本町は、大雪山国立公園も有していますので、環境を第一に考え水素を核にしたまちづくりを進めていきたいですね。
家畜のふん尿から、膨大な水素ができることに驚きました。鹿追町のケースを参考に、クリーンな水素をエネルギーとしてもっと活用できるような施設整備がいち早く進んでほしいものです。
<取材協力>
北海道鹿追町
(取材・文:わたなべひろみ/写真:鹿追町 /編集:奥村みよ+ノオト)
[GAZOO編集部]
あわせて読みたい!
コラムトップ
連載コラム
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08
-

-
HKSとスタディがコラボ、BMW向けアフターパーツブランド「HKSTUDIE」立ち上げ
2024.06.08
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08