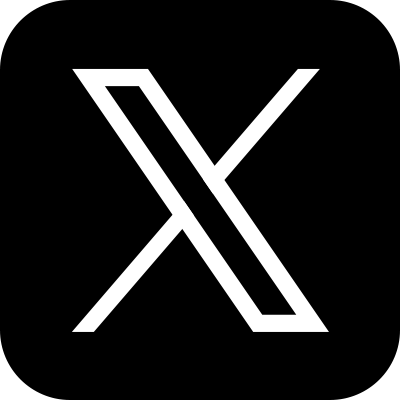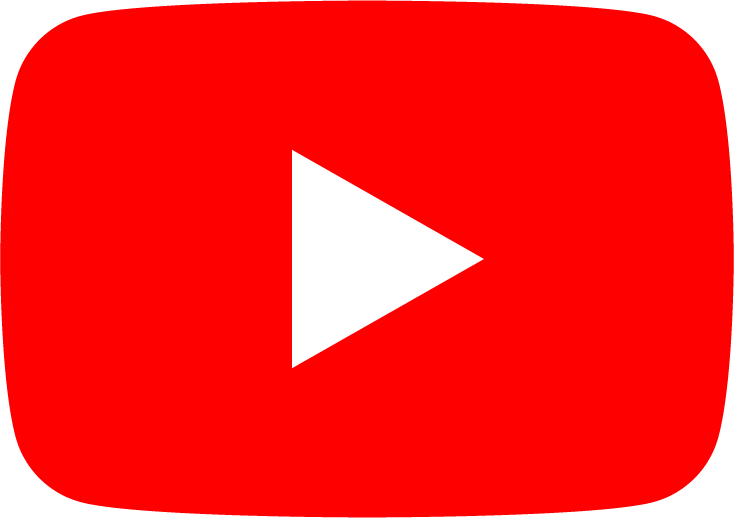「カッコいいデザイン」実現への挑戦。新型プリウスの常識を覆す開発の舞台裏
一般の方の声には「久しぶりにかっこいい日本車」「シンプルなデザインが気に入った」「プリウスらしいスタイル」といった高評価の声が多い。
いっぽう、Aピラーが寝ていることに対して「居住性はどうなのか気になる」、また「19インチの大径ホイールは必要か?」といった、新型プリウスの目玉的なスタイリングに対しての疑問も投げかけられている。
豊田社長に“喧嘩”を売る!? 『愛車』としてのプリウス開発へ
そもそも新型プリウスの開発に向けて、トヨタ自動車の豊田章男社長からは、「プリウスを、タクシー専用車にしてはどうか」と真の『コモディティ(一般的な商品)』としての開発が提案されていたという。
しかし、開発チームは豊田社長にあえて“喧嘩”を挑むこととなる。
『コモディティ』としてではなく、プリウスを『愛車』として選んでいただけるよう「妥協のないクルマ」を造ることを選んだのだ。
その宣戦布告となったのは新型プリウスのデザインであり、それを豊田社長が「カッコいいね!」と受け入れたことで、開発が進められることとなった。
つまり、新型プリウスは最初から高いハードルが設定されていたのだ。
それを乗り越えるため、そして「カッコいいデザイン」を実現するため開発チームが一丸となり、これまでの常識に捕らわれず、新たな発想、技術、運転のしやすさなどへの多くの挑戦があったという。
数値だけに捕らわれないデザインへの挑戦
-

新型プリウスのワールドプレミアの中で映し出されたデザインスケッチ
まず、開発チームが一丸となり頑張ることができた一つのきっかけが、デザイナーが描いたデザインスケッチだという。
通常クルマのデザインは、複雑に絡み合う開発要件によって、当初のデザインとは離れていってしまう場合が多い。
しかし新型プリウスにおいては、「カッコいいデザイン」を優先し、さまざまな挑戦をしながら開発が進められたという。
クルマのスタイリング面での挑戦としては、例えばCD値(空気抵抗係数)だ。
4代目プリウスの場合、効率優先で細かく設定された「あまりにも厳しい」CD値をクリアするために、スタイリングに対してデザイン的な要素はほとんどなかったという。
「CD値は4代目の時のように具体的な目標数値を立てたわけではありません。CD値はじゃあ何のためにあるのかというと、操安性もありますが、最終的には燃費に大きく関わってきます。
でも燃費の改善は、CD値だけが答えではありません。Aピラーを寝かしたことで空気の抵抗は少し減りますから、結果的に燃費が改善できるとか、全体的な大きな目標の中でデザインをしています」
実際に5代目プリウスは4代目よりもCD値は若干悪くなっているというが、それでも燃費性能は4代目以上の数値となっているようだ。
また、Aピラーを寝かしたことで車内空間は多少狭くなっている。しかしこれは、4代目ではCD値を上げるためにあった“不必要な室内空間”を削ったことによるもので、実際に運転席に座ってみても狭いという印象はなかった。
-

新型プリウスのデザインのコンセプト
そして、デザインもより多くの、特に日本人に受け入れられる「普遍的なデザイン」とは何かということを追い求めたという。
「今のクルマのデザインは日本人の感覚とは違うことをやっているのではないかと思っていました。改めて美しいということを考えてみると、なるべくシンプルであまり要素が多くないこと。プリウスでいうと少し路線の変わった4代目から、2代目、3台目のすっきりした路線に戻した、それが本来の居場所なんじゃないかなと感じています」
デザインと走りを両立する新たなるTNGAへの挑戦
また、ボディ設計でも大きな挑戦をすることとなった。まず、「カッコいいデザイン」を象徴する大径タイヤを履かせることだ。
今回19インチのホイールを履かせることで、直径で60mmもタイヤサイズが大きくなっているため、ハンドルを切った際にタイヤが干渉しないようボディ形状を変更している。そして、その半径分の30mm車高が上がるわけだが、理想の乗降りのしやすさのためにヒップポイントも30mm下げているのだ。
4代目のプリウスは、パワートレーンユニットとプラットフォームを一体的で開発しているTNGA(Toyota New Global Architecture)を初採用し、その走行性能のは高く評価されている。
しかし、その技術をそのまま活かすのではなく、デザインのとおりにタイヤを大きくするため、プラットフォームを変更してきたのだ。
さらに、構造や素材も工夫し、特にフロント部分の剛性を上げたり、軽量化を図るなど、TNGAを第2世代に昇華させた。
そのことにより、よりハイパワーなPHEVやハイブリッドのパワートレーンを採用することもでき、走行性能も向上することができたのだ。
ここにも『コモディティ』ではなく、『愛車』としてのプリウスを追い求めるが故の挑戦があった。
-

新型プリウスのプラットフォームの説明資料
開発担当者は、「ある意味ハイブリッド車が当たり前になってきましたが、プリウスはハイブリッドをリードしてきたという自負があるブランドです。この新型プリウスではハイブリッドでもこんなに楽しいクルマ、ワクワクするクルマが作れるんだよねっていう想いを盛り込みたかったんです」と熱く語る。
全ての性能を一体として発揮させる走りを追及
そして実際に新型プリウスを走らせ、評価する“走りの匠”たちも、「このエモーショナルなデザインに負けない走りを作らなくてはいけない」と奮起していた。
「加速性能、ハンドルを切った時に遅れなく一体感のある応答性、減速のときはブレーキのコントロールがしやすく、アクセルオフした時からしっかり減速していく。日常レベルの走行でも気持ちよく走れるよう、動力、空力、ボディの性能をきれいにつなぎきって、無駄なく使い切るという一気通貫のクルマづくりに一番こだわりました」
そして、より走りを安定させるために新たな機能の開発に挑んでいた。それが「エアロスタビライジングアンダーボデーステップ」だ。
-

新型プリウスの空力性能に関する資料。エアロスタビライジングアンダーボデーステップのイメージも分かる
ボディの下はきれいに気流が流れているようで、実は微細な渦が発生しその流れを阻害しているという。
それに対して、ボディのアンダーパネルに「数ミリ程度の段差」を設けることによって、効果的な渦をあえて発生させることで、スムーズな床下の空気の流れを作ることができるという。
さらに、その渦ごとにわずかながらダウンフォースを発生させるなど、これらは数値上では見えない効果ではあるが確実に空力の安定性を高めているという。
空力の安定感が高まることで、サスペンションは過度に固めることなく、フロントの剛性を高めていることとあいまり、現行のTNGA車両よりも明らかに切り出しの応答性が高く気持ちよく曲がることが実現できたという。
「すべてやりたいことができる開発っていうのはなかなかないのですが、このプリウスに関しては、本当にやりたいことは全部やり切ることができましたし、本当に一体感のある開発が進められました」
この新型プリウスには、「カッコいいデザイン」を実現するために、新たなデザイン思想、第2世代となるTNGA、そしてさらなる乗りやすさ走りやすさの追求など、多くの挑戦が結実している。
ぜひとも、豊田社長と開発チームとの“喧嘩”の勝敗の行方を、みなさんが乗ることで見極めてほしい。
(文:GAZOO編集部 山崎 写真:GAZOO編集部)
連載コラム
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08
-

-
HKSとスタディがコラボ、BMW向けアフターパーツブランド「HKSTUDIE」立ち上げ
2024.06.08
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08