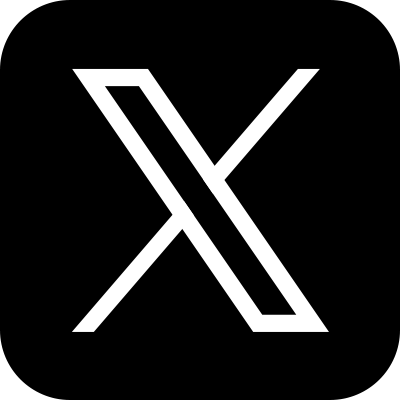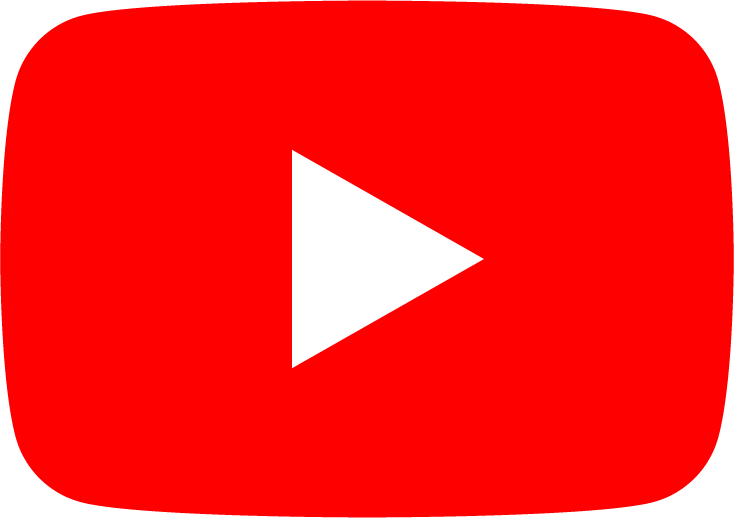スバル車に魅了されたオーナーがたどりついた、スバル360(K111)の独創性とは? 【取材地:北海道】
長距離移動や雪道走行など、本州にくらべるとちょっと過酷なイメージがある北海道のカーライフ。となると、ドライバーが愛車に求める性能もその部分に強い車種やメーカーを選びたくなるのが心情ではないだろうか。
そんな"試される大地"での愛車選びを経て、50年以上も昔の旧車にたどりついたひとりのオーナーさんをご紹介します。
「他の国産メーカー車やヨーロッパ車も持っているし、これまでにもいろいろなクルマに乗ってきましたが、その中でもスバル車は抜群に安定性がよくて長距離運転でも疲れないんですよ」
そう語ってくれたのは、スバル車の持つポテンシャルに魅了され「その原点を知りたい!」と3年前にスバル360を購入するに至った資延泰規さん(52才)だ。
小さな頃からクルマが好きで、若い頃からアウトドア系レジャーを楽しんでいたこともあり、これまでもスバル車だけでレオーネを2台、レガシィを4台と4輪駆動車(以下4WD)を乗り継いできた資延さん。
現在もこのスバル360のほかにレガシィとR1、さらに25年乗り続けているBMWアルピナ、マツダポーターキャブと5台の愛車を所有しているという。
そんな資延さんだが、実は以前は「スバル車はカッコ悪い」と思っていたという。それが一転してスバルフリークになったキッカケが、スバル車の中で最初に乗った2代目レオーネ(AJ5)だった。
「たまたま知人からレオーネがあるよと聞いて『おじさんが乗るイメージだし、欲しくはないなぁ』と思いながらも乗ってみたところ、あまりの乗りやすさに衝撃を受けたんです。安定性や室内の使い勝手、ハンドルの切れ具合など速さ以外の部分、そしてなんといってもボディが良い! 固いわけでも柔らかいわけでもなく、中間かというとそうでもない。でも良い方向に動く感じなんです。薄い鉄板でただ固いボディを作っているようなクルマは乗っているとヘンな共振があるけれど、当時のスバル車は固いんだけどしっかりしている。それを超えるクルマって、自分の中では外車を含めて未だありません」と、レオーネを絶賛!!
こうしてスバルの4WDを大いに気に入った資延さんだが「なぜこんなにもスバル車の性能がいいのか?その原点を知りたい」と思っていた矢先、たまたまイベントでスバル360に触る機会が訪れたという。
「ドアを閉めたときに車体剛性が高いドイツ車のような『ガチン』とした音がして、どうしてこの薄い鉄板でこの音が出るんだろう? これは相当な工夫を凝らしているんだろうな〜と感じました」
そうしてスバル360に興味をもち、3年ほど前に札幌市にある専門店ステップエンジニアリングへ足を運んでこの愛車を購入したのだ。
ちなみに『スバル360』は自家用車がまだまだ普及していない1958年に登場し、12年もの間生産され続けた日本大衆車の元祖ともいえる存在。
「日本初の国民車」と言われるほどの大ヒットを記録した昭和の名車で、可愛らしくてコンパクトで丸みを帯びたデザインから「てんとう虫」という愛称でも親しまれている。
航空機の技術者をかかえる富士重工の強みを生かして、ボディは当時の日本では珍しかったフルモノコック構造とし、日本初のトーションバー・スプリングを採用して室内空間を確保するなど、エポックメイキングなクルマだ。
資延さんが所有するスバル360は1968年製の『デラックス』で、走行距離は約7万kmのMT車。ステップエンジニアリングでほぼ純正の状態に仕上げてもらった車両だ。
やはり気になるのはその乗り味の感想だが「じゅうぶん納得できるものがありました。50年も前の軽自動車なのに骨格がしっかり作られているし、足まわりも砂利道など悪路も多かった当時の道路でも乗りこなせるような配慮がされていて、50年経ったいまでも遜色なく日常の足として使える性能があると思います。クルマの流れの速い北海道でも普通に使用できていますし」と、このスバル360に『スバル車の乗りやすさの原点がある』という確信を得たそうだ。
そんな独創性に溢れた設計が各所に見られるスバル360の魅力を資延さんに伺ってみた。
「丸目が醸し出す圧倒的な可愛さと小ささが一番気に入っています。駐車するときも楽チンですね。そしてこれだけコンパクトなのに、4人乗車もできてなんと身長180cmくらいの人でも中で足を伸ばして寝ることができる作りになっているんです。しかもふかふかで寝心地が良いという(笑)。それとトランクルームが無いかわりにダッシュボードの下に収納スペースが用意されています。狭い空間をいかに広く使用できるか工夫を凝らしたんだなぁと感じますね。ただ、フロントガラスとの距離が近いので、クルマの中で指差しをするとガラスに指が当たったりするのはご愛嬌かなと(笑)」
スバル360のエンジンはリアにあり、ボンネットにはスペアタイヤやバッテリーの収納スペースがあるのみなので、足元の奥行きがとても深く、広い空間が確保されているのだ。
快適性や使い勝手を追求した工夫点は他にも数多い。
「ドアが前開きなのでとても乗り降りしやすいんです。ボディがしっかりしているからこそ選択できた仕様でしょう。またエアコンがないので、走行風を取り込みやすくなる三角窓はもちろん、ボンネットにもダクトがあるんですよ。余談ですが、サイドピラーがないので三角窓まで開けるとちょっとユニークな見た目になるのも好きですね」
「ちなみに、いわゆるダッシュボードと言われる部分が高い確率で劣化しているんですけど、メーカーでは廃盤なんです。とてもシンプルな作りで、レザー風の布を使っても同じようなものができるので自作しました」
というのもじつは資延さん、本業は車やバイク、エンジンなどをお客さんの要望に合わせて作るオーダー専門のぬいぐるみ職人。この程度の加工はお手の物というわけで、違和感もまったくない仕上がりとなっていて、知り合いなどから需要があれば販売もしているという。
「おもしろいのがタイヤの適正値で、0.99kPaととても低い。偏平率が高く、車重も軽いからこれがベストな乗り心地の良さに繋がっているんだと思います。」
このように見どころ満載のスバル360を、資延さんは普段から足代わりに愛用している。
「長距離はレガシィでその次がアルピナ、近距離だったら360と使い分けていて、銀行や打ち合わせなど近場にいく際に乗れるチャンスがあれば乗るようにしています。雨の日は基本的に乗らないようにしているけど、雨にあたっても気にせず後で拭き取るようにしていますね」
またメンテナンスについては、2サイクルエンジン特有のオイル管理くらいだという。
「購入時にステップエンジニアリングさんがしっかり車両整備をしてくださったので、購入してからトラブルは無し。自分でおこなうメンテナンスは、ガソリンと一緒に燃えてしまうオイルの追加作業くらいです」
ちなみにエンジンは空冷で、サイドダクトから取り入れた空気を後ろのダクトから流す仕様となっているのだが、このダクトが旧車らしいスタイリングにも一役買っている。
そんな資延さんは、スバル360の今後について「健康体を保った現状維持」を掲げる。
「このクルマを買いに行ったとき、お店でまずクルマの維持管理ができるのかをチェックする面接が行われ、その上でどの360に乗るかをお店が決めてくれました。というのも『購入金額で買い取るから手放す時はお店に戻してね』というちょっと珍しいシステムになっているんです。つまりお金も出して名義も変わるけど、クルマを一時的に預かる感じになるのかな。僕も結果的にはその方がクルマが大事にされて、後世に繋いでいけると思うし、だからこそ『現状維持』でこれからも乗っていきたい。それに僕は『スバル360初心者』ですから、無理はさせません。といっても、納車時にきっちり仕上げてくれたので、何もしなくていいほど快調ですけどね」
そして資延さんがスバル360を手放さず乗り続ける大きな理由がもうひとつ。
「実は購入時に希望ナンバーではないのに偶然"360"を引き当てるという奇跡が起こったんです。おかげで、軽い気持ちじゃ所有できない十字架を背負わされました(苦笑)」
資延さんが絶対の信頼をおくスバル車の原点であり、50年経ってもその能力を遺憾なく発揮して元気に走り続ける昭和の名車、スバル360。
このクルマをこよなく愛するショップさんの想いも載せて、これからもずっと資延さんの大事な相棒として走り続けていくことだろう。
(⽂: ⻄本尚恵 / 撮影: 木下琢哉(マイナーカラーコード))
[ガズー編集部]
愛車広場トップ
連載コラム
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
「ワイルドなハスラー」登場! スズキ『ハスラー』仕様変更で装備充実、新モデル「タフワイルド」追加
2024.05.31
最新ニュース
-

-
ブレーキキャリパー進化論、ピストン数と性能の関係を徹底解説~カスタムHOW TO~
2024.06.01
-

-
日本モータースポーツの歴史を語って映像で残すプロジェクト「レジェンドレーシングドライバーかく語りき」が5月31日より一般公開を開始
2024.06.01
-

-
スバル『WRX』に「tS」、STIチューンの足回り…米2025年型に設定
2024.06.01
-

-
ランチアがラリー復帰へ、『イプシロン』新型で…212馬力ターボ搭載
2024.06.01
-

-
『グランツーリスモ7』アップデートを配信開始! EG6シビックやGT500のNSXなど追加車種が盛りだくさん
2024.05.31
-

-
BYD、第5世代PHEV発表…エンジン併用で航続2100km
2024.05.31