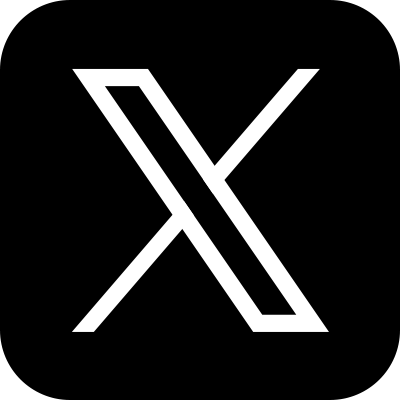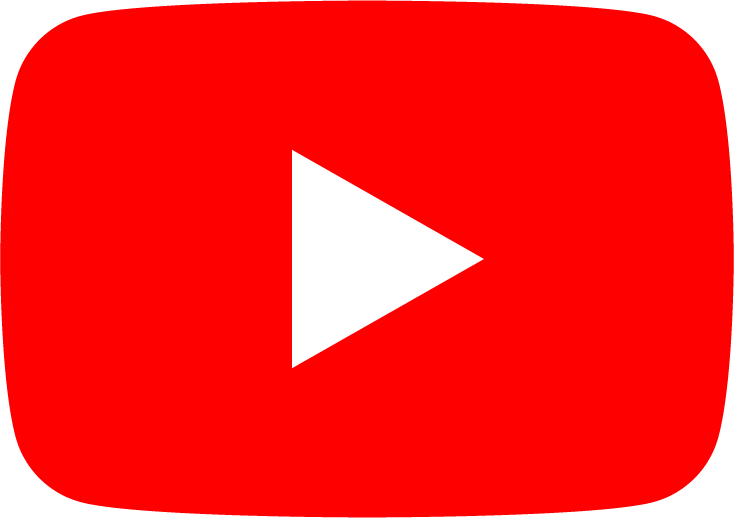10月19日は「レッカーの日」! レッカー車の誕生から最新事情まで
クルマの故障や事故などでお世話になることがあるレッカー車。10月19日は全日本高速道路レッカー事業協同組合が定めた「レッカーの日」です。そこで、レッカー車の誕生から基本的な機能、最新の動きまでを株式会社ヤマグチレッカー 代表取締役 山口喜久雄さんに伺いました。
牽引だけじゃない レッカー車の機能
――レッカー車は最初からレッカー車として一から作られるのですか?
ベースとなるのはトヨタ、日産、いすゞ、日野などのクルマメーカーがつくるトラックです。レッカー車も小型から大型まで用途によってサイズがあるので、つくりたいサイズのトラックを選びそのシャーシーを生かして、レッカー装置を取り付けて製作します。
――レッカー車が必要な時って大抵慌てているので、実はレッカー車の役割ってよくわかっていないように思います。主にイメージするのは動けなくなったクルマの牽引ですが?
牽引、まずはそうですね。あと重要なのは、ひっくり返った状態のクルマを元に戻すという役割です。事故や災害の時にひどい状況で転覆したクルマを引き起こし前を吊り上げて引き上げるといった作業を行います。そのため、クレーン車のようにブーム(荷物を吊り上げるための腕のように伸びる部分)が360度旋回します。
-

クレーン車のように伸びるブームは360度旋回する
――と、いうとクレーン車でも同じ役割ができるのでは?
そう思われがちですが、レッカー車とクレーン車ではワイヤーのウインチ(巻き上げ機)や滑車、フックに大きな違いがあります。クレーン車はブームの先端に滑車がいくつも重なり、小さめのウインチでも重いものを効率よく引き上げられるようになっています。また、フックも大きなものがついているので、動きとしてはワイヤーをまっすぐ下ろして真上に引き上げるという作業が主になります。
一方、レッカー車は、滑車は一つで強力なウインチに小さなフックのシンプルな構造です。フック自体も360度クルクル回ります。ですから、真上に引き上げる動きばかりではなく、横にも下にも斜めにも引っ張ることが可能で動きの自由度がとても高いのです。
クレーン車だと同じような動きを行うと滑車からワイヤーが外れる危険性があります。狭いトンネル内でトレーラーがひっくり返ってしまった場合などは、作業に高さが必要で斜めに引っ張ることができないクレーン車では難しく、レッカー車が活躍するのです。
また、レッカー車はウインチが最低2個ついているので1本のワイヤーとフックでクルマを引き起こしながら、もう一方のワイヤーで抑えるようにして安定を取るなど自在な動きができます。
――形は似ていてもやはりレッカー車の方がよりクルマを引き上げる機能に特化しているのですね。レッカー車としての役割はその他にもありますか。
JAFさんなどの小型のレッカー車は、クルマを牽引するのはもちろんなのですが、いわゆるロードサービスが主な仕事です。普通乗用車のトラブルの90%はバッテリートラブル、ガス欠、タイヤのパンクといわれています。ですから、小型のレッカー車では大抵がバッテリーをチャージする機械やハイオク、レギュラー、軽油の小型の燃料缶、タイヤ交換のための工具などを装備していますね。
-

小型レッカー車は移動修理工場の役割も
――普通乗用車向けのレッカー車というのはクルマを牽引するレッカー車であるとともに、簡易の修理工場が現場に行くようなものなのですね。
そうですね。ちなみに、だいたいのドライバーはこのようなロードサービスの利用も6年に1回くらいだそうですよ。
1916年に誕生したレッカー車はT型フォードに組み込まれていた
――レッカー車というのはいつごろからあるものなのですか?
レッカー車の第一号は、1916年にアメリカのテネシー州チャタヌーガという町で生まれました。GMの修理工場を営んでいたアーネスト・ホルムスさんが事故や故障を起こしたクルマを現場で修理するのではなく、自分の工場に持ってきて直せられれば効率がいいのではと考えレッカー車をつくったといわれています。レッカー(wrecker)はホルムスさんが名付けた造語です。難破船(wreck)を引き上げるといった意味ですね。
初期のレッカー車はT型フォードに取り付けられていました。ホルムスさんが発明した機械式のレッカー車は長らくつくり続けられ、第二次世界大戦の時にはアメリカの軍用車としても使われていました。この機械式のレッカー装置は1990年くらいまで世界中で使われていたのですよ。
-

International Towing & Recovery Hall of Fame & Museumに展示される初期のHolmes(ホルムス)のレッカー車(写真提供:山口喜久雄さん)
そして、70年代中頃にアーネスト・ホルムスさんの孫であるジェリー・ホルムスさんが油圧式レッカー装置を開発し、次第に機械式から油圧式レッカーへと移行していくのです。
アメリカ製のレッカー装置が日本に入ってきたのは1970年代の半ば。今もアメリカ製のものを輸入して使用しています。
日本では、現在、しっかりと設計・構造解析(エンジニアリング)まで行っているレッカー装置製造メーカーはないのです。
――日本でレッカー装置をつくっていたことはないのですか?
戦後に手づくりのレッカー車をつくっていた時期はありました。H鋼を曲げて真ん中にもう一本H鋼を渡したところにチェーンブロックを取り付けてそれでクルマを引き上げるというもの。アメリカ軍が戦地で使っていた地雷回収車の形状からヒントを得て考え出されたそうです。しかし、力学的にはあまり効率がよくなかったため、つくり続けられなかったようです。
-

-

日本製レッカーはチェーンブロックを使用した手づくりだったそう
――では、現在はほぼアメリカ製のものを輸入しているのですね。今、特に必要とされているレッカー車というのはありますか?
近年、自動車保険にロードサービスが当たり前のように付帯するようになってからは、小型のレッカー車は多いですね。それから、バスやトラックを牽引する大型レッカーの需要も増えています。排気ガス規制が厳しくなった2000年以降、特に路線バスの故障が多くなりました。排気ガスの処理を行うシステムというのは、ある程度の高い温度にならないと効果を発揮できずマフラーが詰まってしまいます。路線バスのように動いたり止まったりが多いと高温になりきらずトラブルを起こしやすいのです。普通乗用車であれば動けなくなっても積載車に載せて運ぶこともできますが、バスはそういうわけにはいきませんから、大型レッカーの出番になるわけです。時代とともに故障がなくなるかと思っていましたが、思いのほか増えてきてレッカーが必要とされています。
レッカー車出動! もしもの時に慌てないように
――レッカー車を呼ばなければならない場合に心がけた方がよいことはありますか?
高速道路で故障や事故にあったときには、特に気をつけてほしいのですが、レッカー車が来るまで、できればクルマから降りてガードレールの外側で待っていてください。路肩にクルマを寄せて止まっていたとしても、本線ではクルマが時速100kmくらいで走っているわけです。クルマに追突されてしまったら二次災害が起きてしまいます。
そして、できれば道路緊急ダイヤル「#9910」に電話をし、後部警戒をしてもらえるように連絡をしてください。レッカー車が到着したとしても作業中に追突されるというケースもあるのです。ですから、道路管理者に道路の規制をしてもらうのは大事なことです。慌ててしまうとなかなかそこまで考えが巡らないかもしれませんが、ぜひ覚えておいていただきたいです。
災害に備えてレッカー車にできること
――今後、レッカー車関連での動きというのはありますか?
ここのところ、日本各地で災害が多いですよね。私たちレッカーサービスを行っている者は、24時間365日体制で備えていますが、もちろん災害時にクルマが水没したり、クルマで道路がふさがれたりしたらすぐに出動します。
実は先日、災害対策用のレッカー車を開発しました。5年ほど前から国土交通省では災害時の道路啓開という考え方を広め始めています。道路啓開とは災害により瓦礫などでふさがれてしまった道路を切りひらいていくということ。そうしなければパトカーも消防車も救急車も通れませんから。今回開発したクルマは道路啓開用レッカー車です。水害や雪害の時にも足元を取られないよう車高の高い4輪駆動車となっています。
-

足回りを強化した道路啓開用レッカー車
ただ現状では、災害時、建設会社などはすぐに出動できるようになっていますが、レッカー会社にはダイレクトに情報が来ないのです。道路がクルマで埋まっていたり、消防署の前にトレーラーがひっくり返っていたりしたら消防車は出動できないではないですか。そういうときにレッカーの機材をいかして道路啓開を行う体制を整えられるよう、現在、積極的に自治体や警察などに働きかけているところです。災害はないに越したことはありませんが、もしものためにすぐに動ける体制はしっかり整えておかなければなりませんから。
T型フォードの時代から道路啓開用レッカー車まで。レッカー車はクルマの万が一のときのため、災害時の安全確保のためと進化しています。できればお世話になりたくはありませんが、もしものときの心強い味方としてレッカー車はこれからも発達していくことでしょう。
<取材協力>
株式会社ヤマグチレッカー
(取材・文:わたなべひろみ/写真:株式会社ヤマグチレッカー/編集:奥村みよ+ノオト)
[ガズー編集部]
あわせて読みたい!
コラムトップ
連載コラム
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08
-

-
HKSとスタディがコラボ、BMW向けアフターパーツブランド「HKSTUDIE」立ち上げ
2024.06.08
最新ニュース
-

-
サイドミラー&フロントウインドウに“超撥水”効果を付与! 強力な“雨対策”アイテムに注目!【特選カーアクセサリー名鑑】
2024.06.09
-

-
ホンダ『シビック』ハイブリットモデルは200馬力
2024.06.09
-
![[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?](/-/media/TMC/gazoo/news/res/24/06/08/r382718/001/thumb.jpg?la=ja-JP&rev=6b25fd320b74468f939d5d14827155c7&hash=CE218F5DC80EEED5F46DA492BE7C98C5)
-
[ワゴンRスマイル vs デリカミニ]スペック比較…カッコいい/カワいい以外にどこが違う?
2024.06.09
-

-
知らないと危険なボルトの締め方? DIY初心者必見! トルクレンチの重要性と使い方徹底ガイド~カスタムHOW TO~
2024.06.08
-

-
いすゞのSUV『MU-X』、改良新型が間もなく登場…ティザー映像公開
2024.06.08
-

-
エアバッグの位置が! ZFの次世代ステアリングホイール
2024.06.08